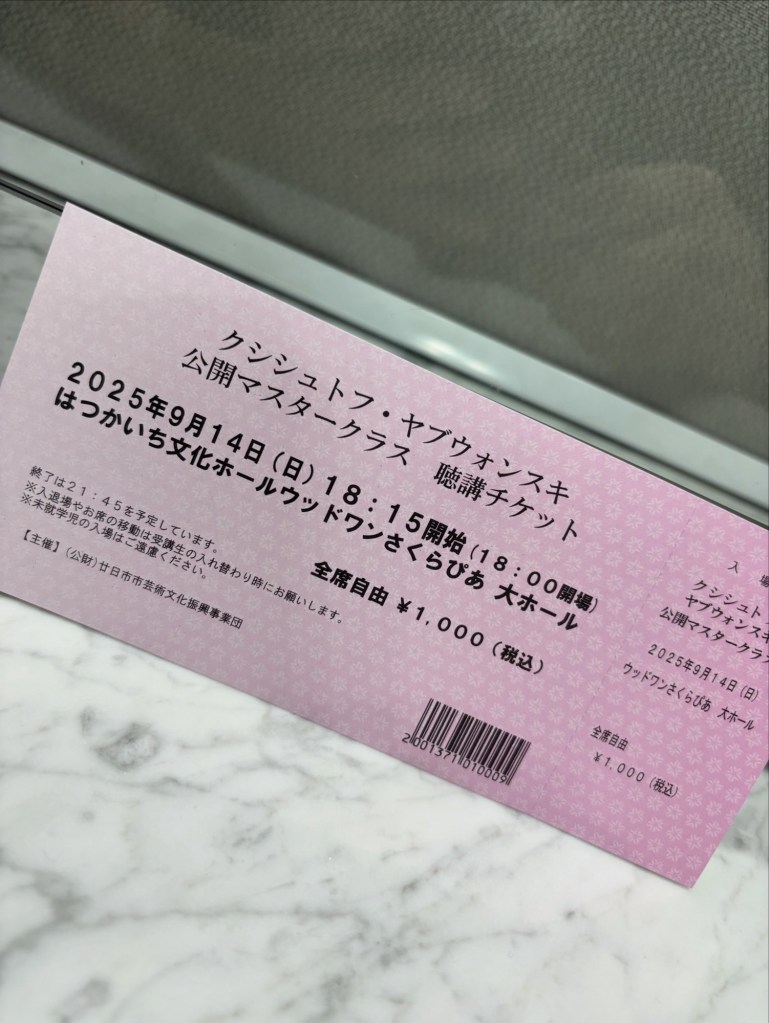





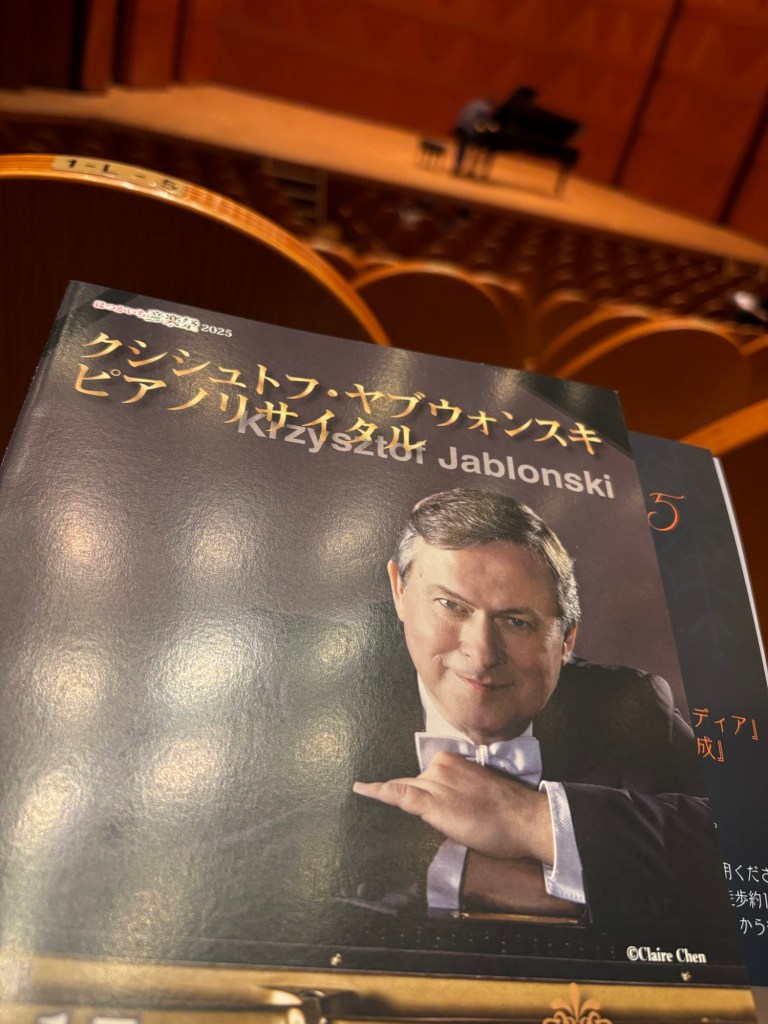
ヤブウォンスキ氏のピアノリサイタル、そして前日のマスタークラス。
この二日間を通して、私は心の底から「行って良かった」と思えた。
彼の演奏の根底には、徹底した「無駄のなさ」がある。
弾きすぎない。けれども、その抑制の中にすべてが込められている。
あの音量で、十分に表現は伝わってくる。
楽譜に書かれていないことを加えることはなく、かといって無味乾燥になるわけでもない。
テンポは崩れず、ペダリングは濁らず、和声の移ろいが澄んだ光のように響いていく。
旋律は旋律のままで、決して和声に埋もれない。
アゴーギクやルバートは「適度に」、つまり音楽が自然に呼吸する範囲に留められる。
特に心に残ったのはスタカートの扱いだ。
書かれていないアクセントは決して付けられず、スタカートは正しい解釈で奏でられた。
その一音一音の軽やかさと確かさは、重力奏法を自在に操れるからこそ可能なのだろう。
腕や指の力で叩きつけるのではなく、自然な重力をコントロールし、響きを保ちながら切る。
あのスタカートを耳にして、「これこそ正解だ」と思わずにいられなかった。
マズルカには涙を誘われた。
言葉では到底言い表せない、魂に届く響きがそこにあった。
そしてソナタ第3番。
あの清潔で繊細、しかも美しい演奏を、これまで耳にしたことがあっただろうか。
ペダリングは神がかり的で、すべてがドラマティックに展開していった。
スッキリとしていながら壮大で、矛盾のない音楽の流れがそこにあった。
マスタークラスでの彼の指導、そして最後のインタビューから、
「日本人が弾くショパン」をどう見ているのか、何となく想像できた気がする。
日本のショパン解釈は、これからどう変わっていくのだろうか。
ヤブウォンスキ氏の存在は、その問いを私の心に投げかけている。